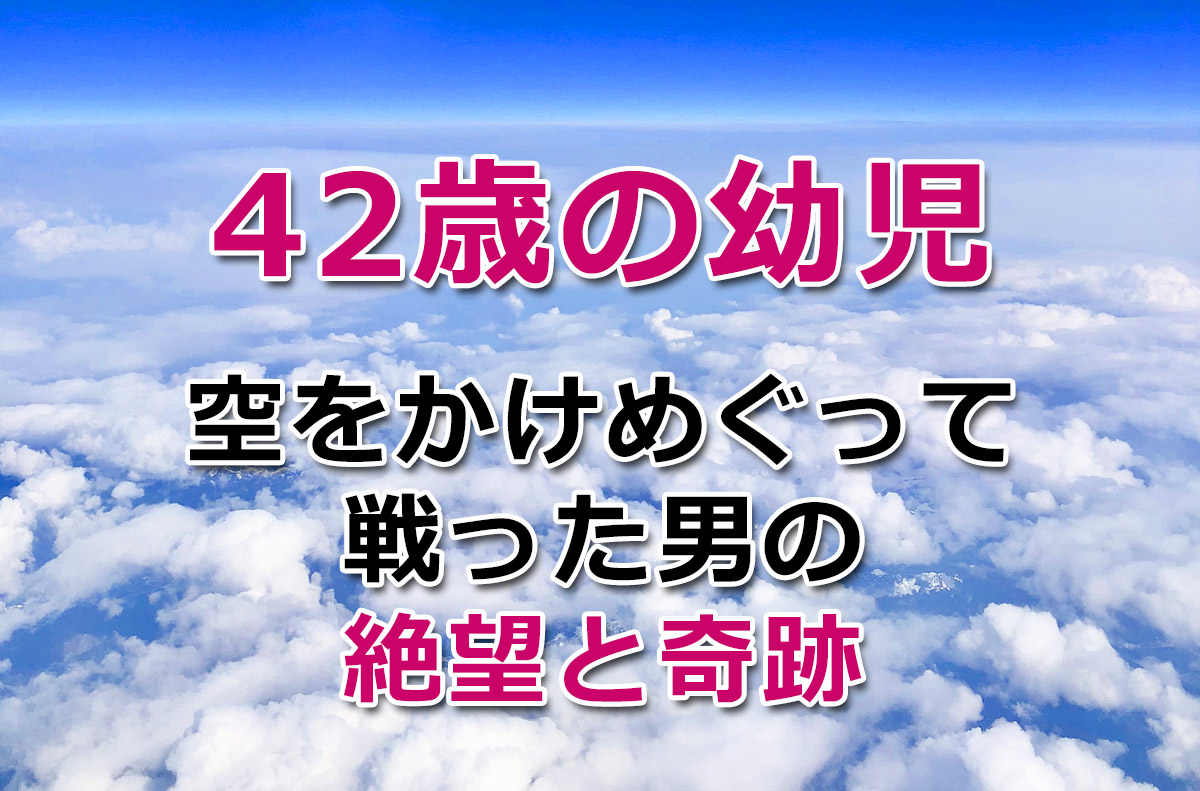
2001年7月8日。
アメリカ、コネティカット州のリハビリテーション施設。
一人の男が、スタッフの助けを借りながら、プールに浮かんでいた。
首に浮き輪、腰には救命ベルトをつけている。
周囲には、家族や理学療法士、ドキュメンタリー映画のクルー、その他関係者たち、大勢の人々が固唾を呑んで男の動向を見守っている。
彼の足首に重りが付けられ、胸の辺りまで水中に沈んだ。
このまま力を入れて膝を伸ばせば、水中で立ち上がることになる。
理学療法士が聞いた。
「立ってみますか?」
男は答えた。
「もちろん」
準備が整うと、彼は心の中で自分自身に「ゴー」サインを出した。
脳が「立つのだ」という指令を出すと、筋肉が緊張して膝が伸びた。
身長192cmの男は、水中で直立した。
みんなが、まるで月ロケットの打ち上げ成功のときのように、歓声を上げた。
これは何事なのだろう?
男の挑戦は、まだ終わっていない。
肝心なのはここからだ。
理学療法士が言った。
「全体重を右足に移してください。そして、左足を前に蹴ってください」
男は左足を前に蹴ってみる。
自分の目で、左足が前に出たのが見えた。
できた!
「今度は左足に体重をかけて、右足を蹴ってください」
これを続けるうちに、彼の「体」は、今何をすべきなのかを覚えていった。
「歩くこと」
それは、彼にとって全く不可能なはずのことだった。
以前彼は、事故で「四肢麻痺」となり首から下が全て麻痺した。
何年もの間、手足の動作はできず、感覚すらなかった。
しかし、不屈の努力と訓練の末に、水中でだが、初めて自力で歩くことができたのだ!
男の名前は、クリストファー・リーブ。
「スーパーマン」を演じた俳優です。
映画シリーズ4本に渡り、空をかけめぐって戦い、地球を守った男です。
今回は、以前公開した「飛べなくなったスーパーマン」の続編です。
人体という精密機械
人間の体はいわば、精密機械のようなものです。
我々が想像するよりも、はるかに複雑でデリケートです。
体を調整する部品が失われたり、故障してしまうと、それまでは当たり前のように動いていた体が、動かなくなることがあります。
息をするのも
食べるのも
排泄するのも
起き上がるのも
全て脳と体が綿密に連携して、動作しているのです。
脳と体の連携が失われたとき、我々はいったいどうなってしまうのか。
「プールの奇跡」から遡ること6年前。
当時42歳のクリストファー・リーブは、落馬事故によって頚椎を損傷し、首から下が全く動かず、感覚もなくなりました。
自力で呼吸ができません。
おそらく、生涯にわたって、生命維持のケアに頼って生きていくしかない。
二度と、自力で手足を動かすことはできない。
それが、一般の医師の見解でした。
42歳の幼児
事故後のリーブの日常は、こんな様子です。
リハビリセンターでは、一日一度病室から「娯楽室」に移動するという日課がありました。
お見舞いの人に会ったり、家族に手紙を読んでもらうためです。
そしてこの移動が、とてつもない大冒険だったのです。
「娯楽室」に行くには、車椅子に乗る必要があります。
そのためには、まず「上半身を起こす」のですが、いったい彼にどんなプロセスが必要なのかわかるでしょうか。
看護士と理学療法士が、彼の頭と首を硬い輪に固定します。
胴体のほとんどを、補強用帯布でぐるぐる巻きにします。
これは、起き上がったときに血圧が下がるのを防ぐためです。
次に、プラスティックシートを体の下に敷き、体を横向きに転がしてもらい、シートを定位置に滑らせてもらう。
問題はここからです。
ベッドの上で、徐々に座った姿勢になるように体を起こされていく。
血圧は、90秒ごとにモニターされます。
このとき、途中で気を失うことがあるのです。
そうすると、再開まで10~15分は待つことになります。
調子が悪いときにはこれを2~3度試し、調子が良いときは、血圧が落ち着いたまま20分ほどで起き上がれることもあります。
起き上がれたら、ようやくゆっくりと車椅子に体を収めてもらう。
そして、やっと「娯楽室」に向かうのです。
毎回、こうした複雑極まりないプロセスが必要なのです。
健常者は、この「起き上がり、座る」という動作を、自分の体の調整と筋力で、さして意識することなく行なっていますよね。
こうして、日常の最低限の営みをするにも誰かに頼らなければならない。
リーブは自身のことを、こう思っていました。
麻痺によって、自分は「42歳の幼児」に変身してしまった、と。
希望と絶望の日々
事故直後の彼は、希望と絶望が入り混じった状態でした。
「大丈夫、やがて良くなるはずだ。」
「これまで自分は、どんな怪我も病気も乗り越えてきた。だから、この麻痺を
乗り越えられないわけがない」
「一生動けなくなるなんて、あるわけがないし、そんなことはとても受け入れられない」
しかし、状況を知るにつれて、それが紛れもない現実であること、そして事態が深刻であることを、理解していったのです。
リーブは、やり場のない絶望と怒りに翻弄されました。
「一体これまで自分が、どんな悪いことをしたというのか?」
「なぜ、自分だけがこんな「罰」を受けなければならないのか」
そして、自殺願望にとりつかれました。
「もう、死なせてもらったほうがいい」
リーブは、妻のディナにそう言いました。
そのとき、ディナは大きなショックを受けながらもこう言いました。
「私はあなたの意思を尊重する」
「でも、覚えておいてほしい。私は何があってもあなたのそばにいる」
「あなたはあなたのままだもの」
さらに、こう言ったのです。
「少なくとも、2年間待ちましょう」
「もし2年後にどうしても考えが変わらないのであれば、あなたの望みどおりになる方法を検討しましょう」
賢明なディナは、2年経ったらリーブがどういう答えを出すのか、わかっていたのです。
そして、今は沸騰したリーブの気持ちを少しでも冷やそう、と思ったのでしょう。
そこにいるだけで意味がある
リーブは、家族の人生をも変えてしまうことに憤りを感じていました。
特に、子供たちのことです。
二度と動くことのできない自分が、幼い3人の子供たちをどう導いていけるというのか。
もはや、自分は満足な「父親」とはいえないだろう。
いやそれどころか、子ともたちが「生涯麻痺」という事実に衝撃を受けたり、トラウマになったりしないだろうか。
深く憂慮しました。
しかし、現実は彼の想像とは少し違いました。
子供たちは、しょっちゅうリハビリセンターの父・リーブに会いに来るのです。
リーブは、子供たちにこう言いました。
「私は大丈夫だから、こんな気分が滅入るようなところから出て、外で楽しんで来なさい」
何度も、子供たちにそう言い聞かせました。
しかし子供たちは、たとえ面会時間が2~3時間しかなくても、彼と一緒にいたいと言いました。
帰ろうとしないのです。
やがて、子供と接しているうちに、彼は気づきました。
「自分はかつて、こんなにも子供たちと話をしたことがあっただろうか」
今まで彼は、旅行やスポーツ、冒険、何かの日常的な行事など、子供たちと行動を共にし一緒に体験することで、心を通わせ、教えたり、導いたり、楽しんだりしてきました。
それまで、彼のアイデンティティは行動や活動で示すものでした。
しかし、今は動くことができません。
行動で示すことはできません。
にもかかわらず「そこにいるだけで」子供たちにとって意味のある存在になっていたのです。
子供たちといるとき、リーブはかつてないほど子供たちの言葉に耳を傾けました。
子供たちは、リーブの発する言葉ひとつひとつに、影響を受けていました。
「すること」ばかりではなく
「そこにいること」が大事なのだ。
彼は初めて、そう感じたのです。
彼にとって、それはまったく思いもよらないことでした。
リーブは、こうして妻や子供たち、医師や友人たちによって自殺願望から遠ざかり、生きる方向に目を向かされていったのです。
左手の奇跡
奇跡は、左手の人差し指に起こりました。
落馬事故から5年後の2000年。
リーブとディナが話しているとき、ディナはリーブの左手の人差し指が動いているのに気づきました。
それまでも、彼の体の一部が動くことは珍しくなかったようですが、脳と体が連携していないので、それは意思とは関係ない動きです。
だから、その左手の指の動きをディナがたずねると、やはり意識的なものではなく、無意識に動いていただけということがわかりました。
そのとき、ディナはふと言いました。
「じゃあ、意識して動かせるかどうかやってみて」
今のリーブには、脳の命令で指を動かすのはできないことです。
だから、これは2人にとってできてもできなくてもいい、ただのゲームでした。
リーブは、左手の人差し指を見つめて精神を集中しました。
真剣に、精神と体の関係を作ろうと、一心不乱に指を凝視しました。
「動け!」
ついに彼はそう叫びました。
すると、先端から第一関節までが上下に動き、リズム良く肘掛を叩いたのです!
2人とも、信じられない思いで見守っています。
そして再び精神を集中し
「止まれ!」と叫びました。
すると、指は止まりました。
ディナは椅子から飛び上がり、彼の近くに行って再び観察しました。
2度目を行い、成功しました。
3度目はディナが合図を出し、これも成功しました。
4度目は、リーブが目を閉じた状態でディナが合図を出し、これも成功したのです。
しっかりとリーブを抱きしめた彼女の目には、涙が浮かんでいました。
近くで待機していた看護士長も、その知らせを聞いた担当医も、事の顛末に正気を失っていました。
ありえないことが起こったのです。
そしてその後、詳しい検査が行なわれました
果たして、指に「感触」が戻っていたのか、あるいは感覚はないまま動作だけができたのか、それは不明です。
しかし、動くはずのない体を、意思によって動かすことができたのです。
担当医たちは、この奇跡の現象に、我を忘れるほどに興奮したようです。
観衆(医師たち)の前で
その後、彼は医師たち(観衆)に、さらなるパフォーマンスを見せつけました。
人差し指だけではなく、左手の「全ての指」を動かして見せ、さらに、肘掛から垂れている右手首を水平になるまで持ち上げました(!)
そしてさらに、手首を曲げて、手を完全に上に持ち上げたのです。
ただしこれらは、決して「軽々と」できたのではなく、とてつもない集中力とエネルギーをつぎ込んで成し遂げたものでした。
「プールの奇跡」は、それから1年後のことでした。
彼が52歳で亡くなるまで、ついに自力で立ち上がること、そして歩くことはできせんでした。
しかし、指や手の動作やプールでの水中歩行は、医師たちを驚愕させた出来事でした。
我々は「麻痺ゾーン」に生きている
リーブは言います。
障害があろうが健常者であろうが、我々の多くは「麻痺ゾーン」に生きている。
ここでいう「麻痺ゾーン」とは、次のようなことです。
憂鬱というわけではないが、何事にも興味を呼び起こされず、儀式のように同じことを繰り返し受けながら、一日また一日と過ごしていく状態。
問題なのは、もしそのゾーンに長い間はまってしまうと、人生に意味を見出せない状態に取り込まれる、ということ。
そして、その「麻痺ゾーン」が危険なほどに心地よくなるということだ。
リーブの言葉です。
リーブが飛んで行った場所
体は動かないけれど、リーブは精神力で突き抜けました。
できるところまで、歩けるところまで、とにかく歩いたのです。
腐ったり、投げやりになったことなど、数え切れないほどあったことでしょう。
それでもまた、「情熱ゾーン」に飛んで行ったのです。
それは、彼が四肢麻痺の状態で生きていく、ただ一つの方法だったのかもしれません。
彼のエネルギーを、きっと我々も見習うことができるでしょう。
自分でフタをしたままの、まだ見ぬ大きな可能性が、我々にもきっとあるはずです。
ではまた次回!
(クリストファー・リーブの実話およびストーリーは、本人の著書「Nothing Is Impossible(邦題:あなたは生きているだけで意味がある)」より抜粋・引用 調整しています)
当記事は「わかるWeb」のメールマガジンの記事を投稿しています。
「わかるWeb」のメールマガジンは好評配信中です!!
いつでも自由に解除できますので、一度是非登録してみてください!
こちらからどうぞ!
「わかるWeb」メルマガ登録
この記事が面白かった場合には、スターやブックマークをお願いします!
大変な励みになります!


